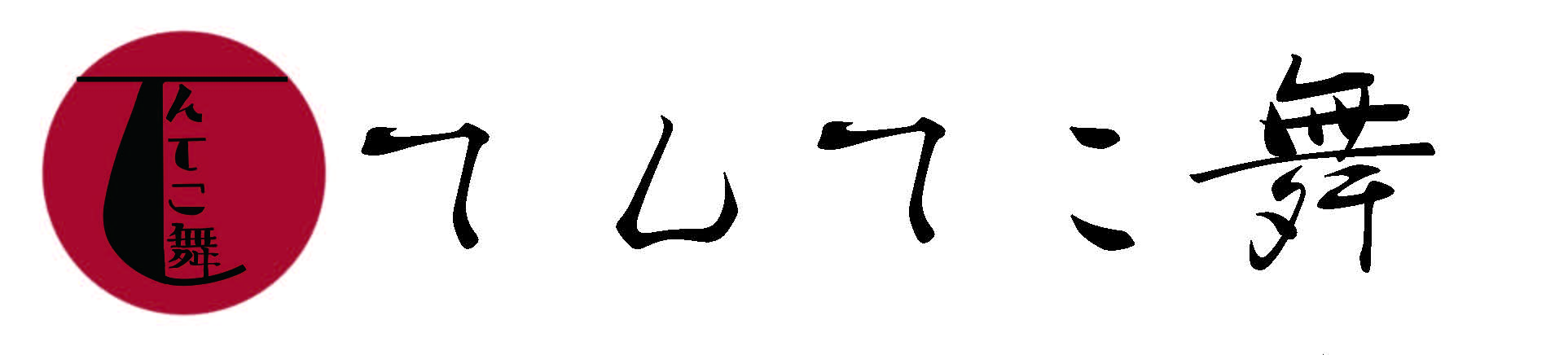第二回 この文字読めますか?-変体仮名入門-
こんにちは!
てんてこ舞ブログ企画 第二回を担当する みゆ です!
今回のテーマは
変体仮名!
日本文学専攻の筆者は授業で変体仮名を習っているのですが、これがとてもおもしろい…!
というわけで、みなさんに紹介します。
私自身、すらすら読めるわけではないのですが、ちょっとでも読めると楽しいですよ。
この記事を読み終わったころには、平安貴族気分になっていること間違いなし!

それではいってみよう~!
そもそも変体仮名って何?
現在日本で使われているひらがなは、平安時代に中国の漢字をもとに成立したもの。
これらの文字には、それぞれ、もととなった漢字が存在します。
たとえば、現在使われている「け」という文字は、「計」という漢字を崩して成立したものです。

↑「計」をもとにした「け」(注)
しかし、当時「ke」の音を表す文字は他にもたくさんありました。



上にあげた3つは、全て「ke」の音を表すひらがなです。
それぞれ、「介」、「遣」、「気」がもとになっています。
他の音も同様で、一つの音を表すのに、たくさんの種類のひらがなが使われていました。
でも、今のひらがなは一音に対して一文字が決まっていますよね。
いったい何があったのでしょうか?

転機は1900年。
小学校令規則により、ひらがなの字体が現在使われているものに統一されたのです。
以降、書道など特別な場を除き、現行の字体以外のひらがなは使用されなくなりました。
この、小学校令規則で採用されなかった字体のひらがなたちが、変体仮名と呼ばれるものです。
実際に見てみよう
ここからは、実際にどんな文字があるのかご紹介!
今回は、私が習ったものの中で、おもしろいと思った変体仮名を3つ発表します!
みなさんも読めるかチャレンジしてみてください💪
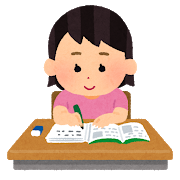
【その1】

これは何と読むでしょうか?
これは、「す」の変体仮名で、「須」という文字がもとになっています。
言われてみたら「須」の面影を感じなくもない。
ぱっと見では、現行の「に」や「た」を思い浮かべてしまいそうですね。
【その2】

次はこちら!
あれ、現行の「み」じゃないの?
って思った方が多いのではないでしょうか?
実はこれ、「の」の変体仮名なんです。
もとの漢字は「能」。
さっきと違い、あんまり面影が見えない…
ちなみに現行の「み」はこちら↓

これは、「美」がもとになっています。
2画目の流れる向きに注目すると、区別できそう!
この二つは、慣れると割とすぐ見分けられるようになる(気がする)
【その3】
最後はこちら!


みなさん、読めますか?
現行の「の」や「う」に似ていますよね。
これは「か」の変体仮名で、「可」という文字がもとになっています。
意識してみると、何となく「可」が見えるような…?
それにしても、シンプルにしすぎでは。
実際に読んでいると、他の文字より小さく書かれていることも多く、分かりにくい。
ちなみに登場率はかなり高めです。
覚えておくといつか使えるかも…?
おわりに
いかがでしたか?
現在ではほとんど見ることがなくなってしまった変体仮名ですが、お店の看板などで使われていることも、
今回ご紹介したもの以外にもたくさんあるので、ぜひ調べてみてくださいね🤗
早稲田の授業にも、変体仮名を読む授業はたくさんあるので、興味を持った人は今すぐシラバスをチェック!
私ももっと読めるようにがんばります💪🔥
最後まで読んでくれてありがとうございました!
次回の投稿もお楽しみに🌸
(注)仮名の画像は全て以下より引用
・変体仮名を調べる 変体仮名 五十音順一覧